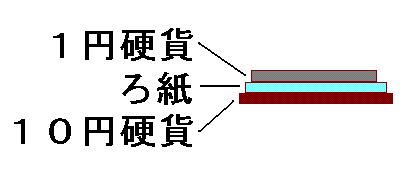 11円電池の模式図
11円電池の模式図(C)TOSSランド>教師ランド>理科>中3>物理・エネルギー>エネルギーの変換>エネルギーの変換
冨田茂(法則化中高草津・法則化中学/アトム)
人類が知っている発電方法は現在、電磁誘導と電池だけである。中学理科からイオンの単元がなくなり、電池の学習は大変薄くなってしまった。電池は身近な物質で作ることができる。是非扱ってみたい実験である。
用意する物(各班に)
10円硬貨×3、1円硬貨×3、ろ紙(1㎝×1㎝、フィルムケースなどに入れておくと良い)×3、電子メロディー、
電解質溶液(5%食塩水など)
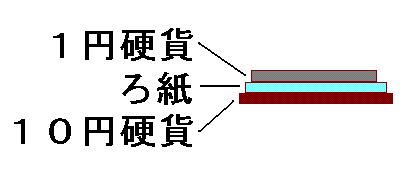 11円電池の模式図
11円電池の模式図
身振りで静かにさせ、紙袋から11円電池で鳴っている電子メロディーを取り出す。
電子メロディーは生徒に見えているが、11円電池は左手に隠してある。
聞こえる?
生徒全員が電子メロディーの音楽に気づいたら
発問1 さて、先生は左手に何を持っているでしょう?
S:電池です。
説明1 電池なんですが、乾電池でもボタン電池でもないんです。
隠している11円電池を見せる。11円電池の部品を一つずつ確認する。
説明2 10円硬貨。1円硬貨。食塩水を染みこませたろ紙。電池なんですが硬貨でできているんですね。今日は電池を作ります。
班ごとに実験道具を取りにこさせる。
このとき電子メロディーだけは渡さない。これを渡してしまうと、教師の指示を待たずに勝手に鳴らす生徒がでてくる。
指示1 10円硬貨を1枚持ちます。ろ紙を1枚乗せます。さらに1円硬貨を乗せます。これだけで電池になります。11円電池です。
指示2 ここまでできたグループは、先生に見えるように11円電池を高く上げなさい。。
全班ができていることを確認する。
指示3 まったく同じ物を3つ作って重ねます。
説明3 33円電池です。これくらいになると電子メロディーを鳴らすことができます。
だいたいの班ができた頃を見計らって。
説明4 電子メロディーは赤色の導線を10円硬貨に、黒色の導線を1円硬貨につなぎます。
指示4 33円電池ができた班は、電子メロディーをとりに来なさい。
すべての班が電子メロディーが鳴ったことを確認したら、片づけさせる。
発問2 10円硬貨は何という金属でできていますか。
銅です。(知っている生徒も多い)
発問3 1円硬貨は何という金属でできていますか。
アルミニウムです。
説明5 2種類の金属と電流が流れる水溶液があれば、電池を作ることができます。
よくある失敗1
電子メロディーの+(赤い導線)と−(黒い導線)を逆につないでいる。→逆につなぎ換えさせる。
よくある失敗2
33円電池を作るときに、11円電池と11円電池の間にろ紙を挟んでいる。→11円電池どうしの間には何もはさまない。
よくある失敗3
10硬貨の表面が錆びていると食塩水との間で化学反応を起こしにくい。→うすい酸につけておくときれいになる。事前に教師がやっておく。
付記
11円電池はろ紙が湿っているのでボルタの電池と同様「湿電池」である。現在広く使われているマンガン電池、ニッケル電池、アルカリ電池、リチウム電池などはすべて乾電池であるが、原理的には同じ方法で発電している。
日本の硬貨の成分表
| 1円硬貨 | アルミニウム100% | |
| 5円硬貨 | 銅60〜70%、亜鉛30〜40% | 黄銅 |
| 10円硬貨 | 銅95%、亜鉛3〜4%、錫1〜2% | 青銅 |
| 50円硬貨 | 銅75%、ニッケル25% | 白銅 |
| 100円硬貨 | 銅75%、ニッケル25% | 白銅 |
| 500円硬貨 | 銅72%、亜鉛20%、ニッケル8% |